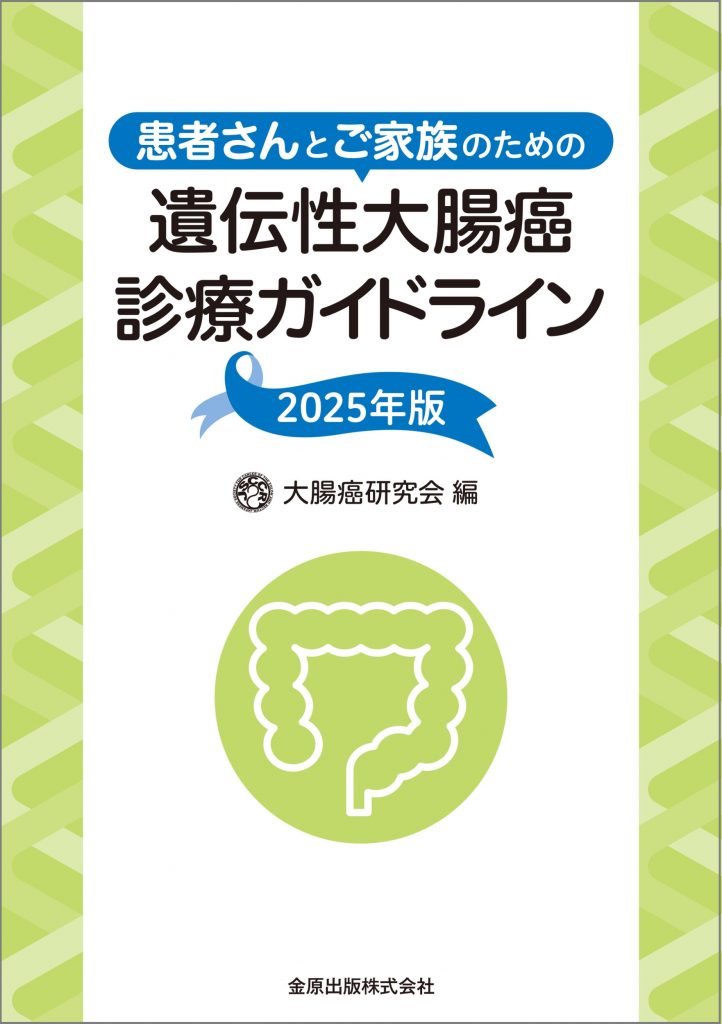大腸癌研究会は日本における大腸がんの研究・診療を牽引する学術団体です。その大腸癌研究会が編集した患者さん向けの書籍「患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2022年版」から,内容の一部をご紹介します。
※ 図は書籍でご確認いただけます
大腸癌にならない予防法はありますか?
がんの予防に関しては国立がん研究センターをはじめとする研究グループで多くの調査がなされています。その中で日本人のがん予防には,禁煙,節酒,食生活,身体活動,適正体重の維持,感染の6 項目が重要であると考えられています。このうち“感染”以外の5 項目は生活習慣に関わるもので,これらを気をつけた生活をおくるとがんのリスクはほぼ半減するということが示されています。
大腸癌に関しては,確実にそのリスクを上げるものとしては,喫煙,アルコール,ほぼ上げることが分かっているものとして肥満があげられています。また女性においては加工肉/赤肉の摂取がリスクを上げる可能性があるとされています。一方で,運動は大腸癌のリスクを下げることがほぼ確実といわれ,他にリスクを下げる可能性があるものとしては,食物繊維,カルシウム,魚由来の不飽和脂肪酸(ふほうわしぼうさん)などが報告されています。また女性においてはコーヒーがリスクを下げる可能性があるとされています。
ただし,大腸癌の発生を確実に抑える有効な予防法は,現在のところ確立していません。大腸癌に限らず生活習慣病を予防するためには,バランスの良い食事,適度な運動,規則正しい生活を心がけることが大切だといえます。
ステージⅢの大腸癌といわれました。ステージとは何ですか?
「ステージ」は「病期」ともいい,大腸癌の広がりの程度を表したものです(14 ページ図10 参照)。ステージ分類には日本の大腸癌取扱い規約分類と国際的なTNM 分類があります。どちらの分類でも,癌が大腸の壁のどの位の深さまで進んでいるか(壁深達度),リンパ節にどの程度転移しているか(リンパ節転移),肝臓や肺などのほかの臓器に転移しているか(遠隔転移)によりステージ0 からステージⅣに分けられています。治療前にCT などの画像診断でステージ(臨床分類ステージ)を予測し,切除された大腸などの組織を顕微鏡で調べた結果をあわせて最終的なステージ(病理分類ステージ)を決定します。大腸癌の治る可能性や,逆に再発する可能性をステージから予測できるため,治療方針の決定に役立ちます。
ステージⅢは,遠隔転移がなく,癌の周囲にあるリンパ節に転移があることを示しています。この場合,手術後に抗がん剤による補助療法を行うことが奨められています(42 ページ「ステージ0~ステージⅢの大腸癌の治療」参照)。
早期大腸癌だから内視鏡で切り取ることができるといわれました。お腹を切らなくてもよいのでしょうか?
大腸癌は大腸の粘膜(6 ページ図5 参照)から発生し,大腸壁の深い方へと浸潤(しんじゅん)していきます(13 ページ図9 参照)。早期大腸癌とは,癌の浸潤が粘膜下層(ねんまくかそう)そうまでにとどまっている癌で,粘膜内癌(ねんまくないがん,Tis 癌)と粘膜下層癌(T1 癌)に分けられます(14 ページ図10 参照)。Tis 癌は転移しないので,内視鏡により癌が完全に取り切れれば,治療は完了です。一方,T1 癌の場合は,遠くの臓器に転移する頻度は少ないものの,リンパ節に転移している可能性が10%前後あります。
癌の存在する部位,大きさ,浸潤の深さなどを総合的に評価して,癌病巣を安全かつ完全に切除することができると判断される早期大腸癌が内視鏡治療の対象となります。内視鏡で切除された癌は,顕微鏡を用いた詳細な検査(病理検査)に提出されます。この検査により癌がすべて取り切れたかどうかを調べるとともに,Tis 癌かT1 癌かが判定され,T1 癌の場合は,リンパ節転移の危険性が評価されます。Tis 癌や転移の危険性が低いT1 癌と判断された場合は,内視鏡治療で治療は完了し,転移の危険性が高いT1 癌と判断された場合は追加の治療としてリンパ節郭かく清せい(25ページ図21参照)を伴う腸切除が考慮されます。
良性のポリープは癌になることはありますか?切除した方が良いのでしょうか?
良性のポリープでも放置すると癌になるものがあります。そのひとつに「腺腫(せんしゅ)」とよばれるポリープがあります。腺腫は大きくなるほど癌が発生するリスクが高くなるため,径6 mm 以上の腺腫は内視鏡的摘除の適応と考えられています。また,「過形成性(かけいせいせい)ポリープ」とよばれるポリープは,「腺腫」に比して癌発生のリスクが低く,切除せずに放置する場合がほとんどです。一方,「鋸歯状病変(きょしじょうびょうへん)」とよばれるポリープは一部に癌発生のリスクを有するものがあり,径10mm 以上の病変を治療の適応とする施設が多いようです。すなわち,良性のポリープは「腺腫」なのか「過形成性ポリープ」なのか「鋸歯状病変」なのか,大きさはどの程度なのか,といったことを確認して切除するかどうかを判断しています。
大腸癌手術の入院から退院までの経過はどのようになりますか?
手術を行う医療機関や病状により多少異なりますが,一般的な手術の流れについて説明します。
1 ) 入院前または入院後:手術前に必要な一般的な検査として心電図や呼吸機能検査,血液検査を行い,手術に十分耐えられるか,検討します。
2 ) 手術前日は食事を中止し,下剤を飲んでいただき,腸の中をきれいにします。
3 ) 手術後の当日は,ベッド上で安静となります。
4 ) 手術翌日:起き上がり,可能なら歩行を行います。状態により水分摂取を開始します。
5 ) 手術後2~4 日:腸の動きに合わせて食事を開始します。
6 ) 手術後3~7 日:おならが出て,排便もあります。
7 ) 手術後7 日以降:食事摂取が可能で,排便も順調であれば,体調により退院が可能となります。手術後10 日~2 週間で退院するのが一般的です。
大腸癌の手術後にはいろいろな合併症が起こり得るとの説明を受けました。詳しく教えてください。
手術が原因となって生じる別の病気や症状を術後合併症(じゅつごがっぺいしょう)といいます。薬の副作用に相当するもので,最大限の注意を払って治療を行っても一定の頻度で発生します。
大腸癌のおもな外科的合併症には,出血,縫ほう合ごう不ふ 全(ほうごうふぜん),吻合部狭窄(ふんごうぶきょうさく),腸閉塞(ちょうへいそく),創感染(そうかんせん),腹腔内膿瘍(ふくくうないのよう),腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニアがあり(33 ページ「手術治療の合併症」参照),他にリンパ漏ろう(リンパ液が漏れでておなかの中にたまること)などがあります。多くの合併症は退院までに起こることが多いですが,吻合部狭窄や腸閉塞は退院してからでも起こります。腸閉塞は手術後何年も経ってから起こることもあり,何度も繰り返す場合もあります。
一方,生命にかかわる重篤な合併症には,肺炎,肺塞栓症(はいそくせんしょう),心筋梗塞(しんきんこうそく),脳梗塞(のうこうそく)などがあります。これらの合併症を予防するためには,手術後なるべく早くから体を動かすことが大切です。手術後なるべく早期に歩いていただくことで,腸の動きの回復が早くなり,また,腸が癒着して腸閉塞になることも予防できます。また,痰も出しやすくなるため肺炎の予防にもなります。足を動かすことで血流がよくなり肺塞栓の予防にもなります。手術の傷は痛いですが,痛み止めを使用しても手術後なるべく早くから体を動かしていただくことが大切です。
これらの合併症は,過誤や過失によるものではなく,患者さんの年齢,全身状態,併存する持病(糖尿病,高血圧,心臓疾患,呼吸器疾患,肝臓疾患など)の影響を大きく受け,同じ医師が同じように注意深く手術をしても一定の割合で不可抗力的に発生します。特にご高齢の方は持病が多く,体を動かすのも遅れることがあり,肺炎や心筋梗塞・脳梗塞などの合併症のリスクは高くなります。合併症に対する治療法は年齢によって大きく変わりませんが,認知症の有無や全身状態により治療方法がかわる可能性があります。手術に伴う合併症により不幸にして命を落とされる方(手術関連死亡率)は,大腸癌の手術を受ける患者さんの1~2%程度と報告されています。
患者さんのための大腸癌治療ガイドライン 2022年版
大腸癌の専門家の先生たちによる患者さんのための解説書が,8年ぶりに新しくなりました。「遺伝子検査」や「ロボット支援下手術」といった,患者さんの気になる最新のトピックを追加しました。さらに,お薬を使った治療の進め方や特徴については表を使い,今まで以上に分かりやすく,詳しく解説しました。大腸癌の治療を進められる中で,患者さんやご家族の方の疑問を正しく解決できる,頼りになる1冊です。
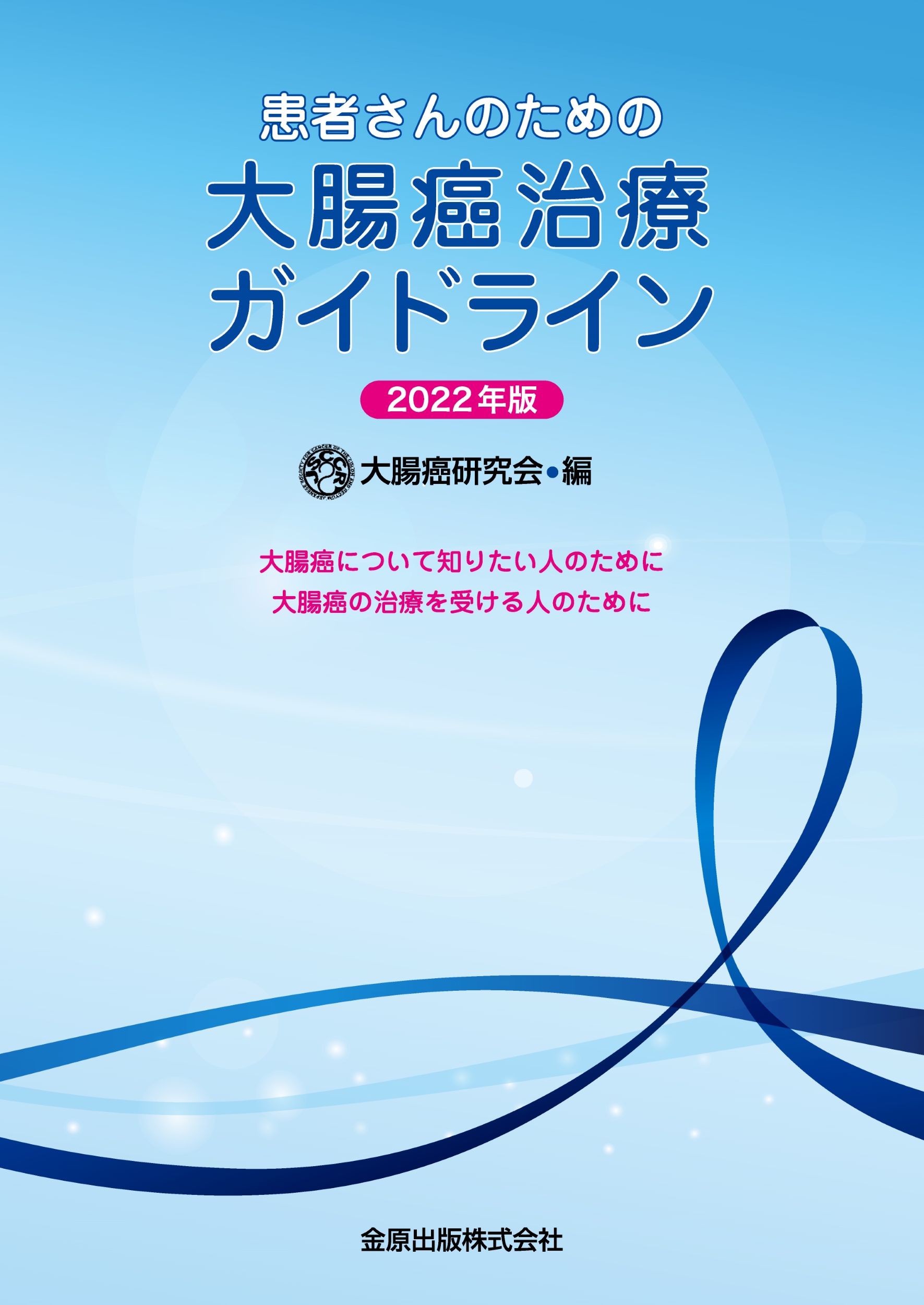
患者さんとご家族のための遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2025年版
大腸癌の中でも遺伝的な要因がかかわる「遺伝性大腸癌」について,患者さんやご家族にも分かりやすく解説しました。検査や治療についての解説はもちろん,「遺伝ってどういうこと?」という遺伝の基礎的なことから,「未成年の子どもに遺伝性大腸癌のことを伝えた方がいい?」「カウンセリングの費用は?」といったお悩みについてもQ&Aでお答えしています。専門の先生たちが作成した,安心できる1冊です。